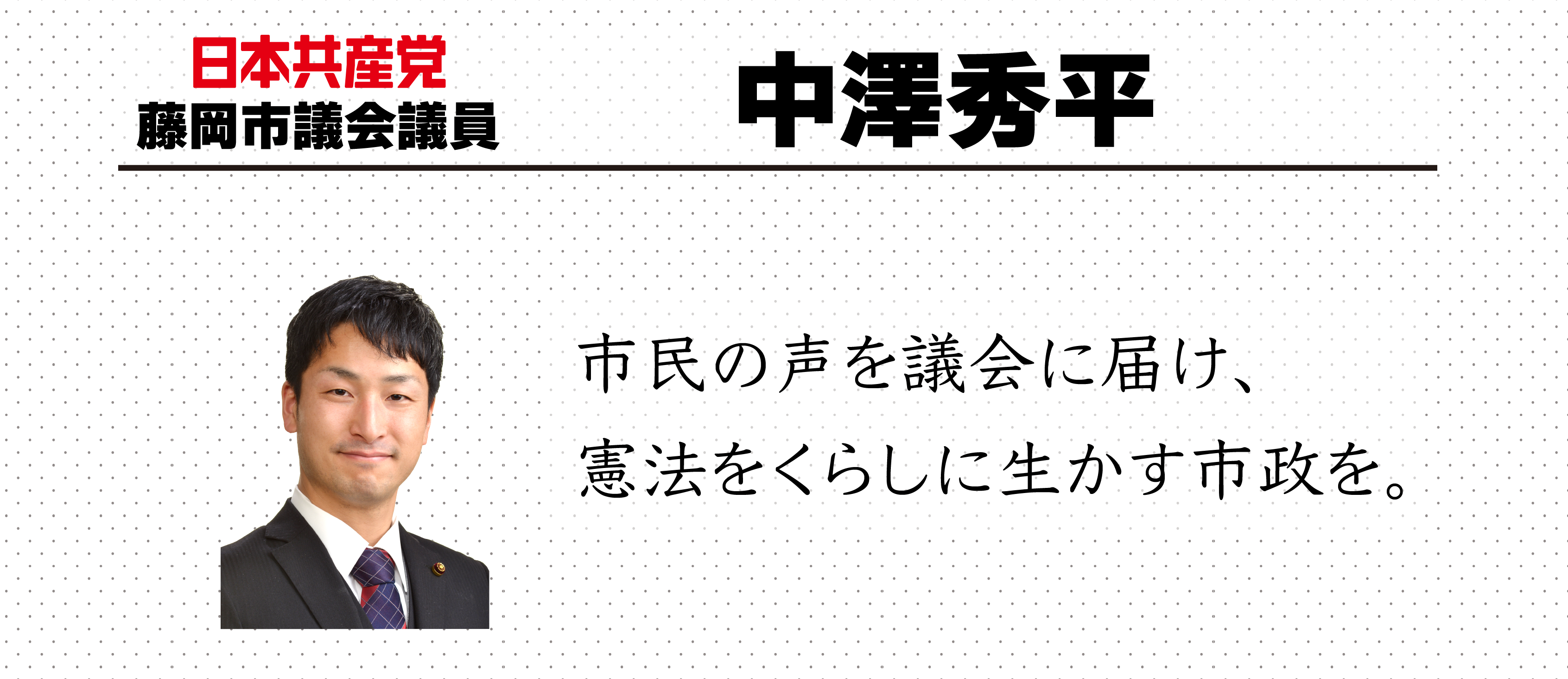住民に一番近い地方自治体の役割を十分に発揮していない、として一般会計・国保特別会計・介護保険特別会計に反対
9月議会最終日の9月19日、一般会計と国保会計、介護保険会計についての決算認定について反対の討論を行いました。物価高などで市民の暮らしが苦しくなる一方、市独自での暮らし応援の事業は少なく、国保料や介護保険料は引き上げとなっています。こうした市政は、国が進める大軍拡による暮らしの予算の削減とも無関係ではありません。国いいなりの市政を許すことは際限のない軍事費の増大を許すことにつながります。住民福祉の増進を旨とする地方自治を十分に発揮させるためにも、特に3会計の決算認定には賛同できないとして反対しました。
以下は反対討論です。
令和6年度藤岡市一般会計歳入歳出決算認定について
市税収入は令和5年度決算と比べて1億3267万4360円少ない約92億円となりました。減収の主な要因は定額減税によるものですが、令和3年度よりの90億円台の税収を維持し、法人市民税では半導体不足の解消や円安の影響で業績が好調に推移した企業などによる税収増で令和5年度と比べて13.6%増、ここ数年でもっとも高い税収となるなど市内経済の良好な一面を示している決算とみることができます。
しかし一方で、収入未済額が増加し収納率は下がっています。また不納欠損額は近年では低い水準に抑えられていますが、その内訳を見れば生活困窮と生活保護受給のための不納欠損処理をしたもので53%を占めていることなど、コロナ禍につづく物価高騰、コメ不足など暮らしの困難が度重なるなかで安定した生活を維持できない市民の様子も浮かび上がっています。
帝国データバンクの調査によると、2024年、令和6年の値上げ品目は前年と比べれば6割減ですがそれでも12520もの品目が値上げとなり、値上げ率の平均は前年の15%から17%と上昇していることが示されています。総務省の消費者物価指数は総合で2.7%の上昇、食料にかぎれば4.3%上昇するなど依然として物価の高騰がつづいている状況が数字にも明らかとなっています。
定額減税や国の臨時交付金を活用した物価高騰対策も実施されましたが、市税の収納率の低下や生活保護世帯の増加が見られることから、その効果は限定的であったと思います。一時的な対策ではなく、いま必要なのは、税の減免適用要件の柔軟な解釈や生活保護基準をもとにした制度の見直しなど、藤岡市独自のとりくみで、いまの恒常的な物価高騰から市民を守る仕組みを整えることです。
暮らしの困難に対しては国の事業や財源に依存し、住民に一番近い地方自治体として役割を十分に発揮できていない藤岡市の姿をあらわす今回の決算について、認定することはできません。
令和6年度藤岡市国民健康保険事業感情特別会計歳入歳出決算認定について
国民皆保険制度の土台とも言うべき国保制度の役割は国民の健康をまもるための医療を保障するすることです。しかし納付率が低下することで滞納が増え、通常の保険証が発行されなくなれば医療を遠ざけることに繋がりかねません。令和6年度より国保税は資産割の廃止にともなって税率が改正されていますが、その結果、被保険者の負担が大きくなり、納付率は現年分滞納繰越分ともに低下しています。
また、昨年12月には保険証とマイナンバーカードの1本化を原則とする運用が開始され、制度が複雑化することによっての負担や混乱も生じています。
国や県全体の社会保険も含めたマイナンバーカードと健康保険証の連携率はともに8割以上となっている一方で、藤岡市の国保加入者の連携率は66%に留まっています。国保加入者には高齢者が多く制度に追いつけないという方が多くいるのではないかと推測されます。
本来立場の弱い人のための制度であるはずの国保が、そうした方たちを置き去りにするような制度へと進める国保行政の決算認定には反対いたします。
令和6年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について
令和6年度から介護保険事業計画が第9期となり、保険料の体型が大きく変わりました。これまで9段階だった保険料の所得段階は13段階に細分化され、第1段階から第3段階までの保険料は基準額に対する料率の引き下げとなりますが、第4段階以上では引き上げとなりました。特に第9段階以上では大きな負担増となります。
高齢者の年金額は物価の上昇と比べれば実質的には減額している状況での保険料負担の大幅な引き上げとなった決算について認定することはできないことを申し上げ、反対討論とさせていただきます。