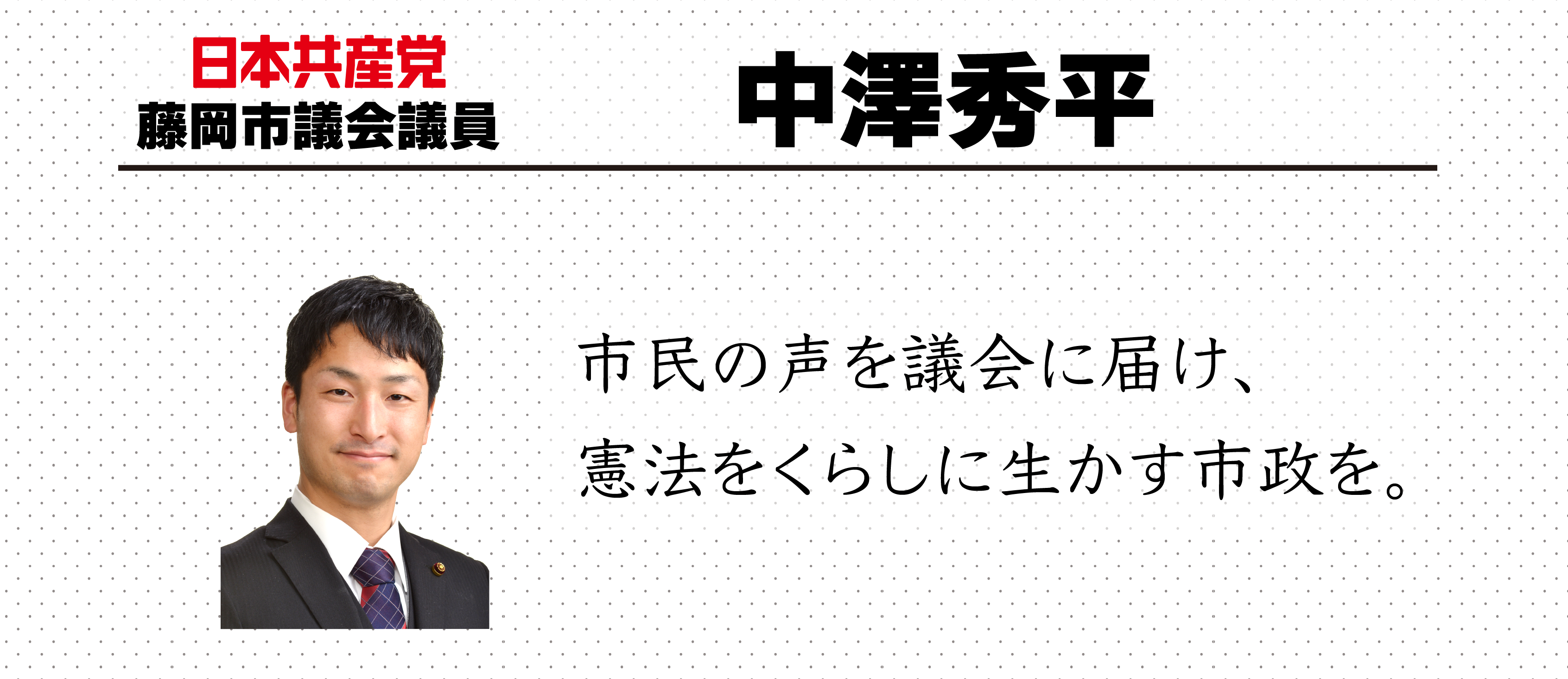高校生の保護者からの相談
先日、市内にある県立高校に子どもを通わせている保護者の方から「部活動のない競技の大会に参加させたいが、学校側からの申請と教員の引率が大会出場の条件で、部活動のない競技はその要件が満たせず参加ができない。」という話を聞きました。その大会は県内の高校が加盟して組織している団体による大会で、加盟校には大会などの参加案内が届いているようです。今回の場合もその高校の校長先生宛に「大会を下記のとおり開催いたしますので、生徒の参加及び貴校関係職員の派遣について、御配慮くださいますようよろしくお願い申し上げます。 」という大会の開催案内が届いていたようです。
しかし、その高校には部活動のない競技のため教員が引率することができず、相談者の方のお子さんは大会に参加することができない、ということでした。
学校現場の苦しい実情
校長先生に話を伺うと「かつて1学年5クラスだったが今では1学年4クラスとなり、それにともなって教職員の数も少なくなっている。そのため部活動自体も少なくしている状況。そのなかで部活動以外の活動まで手を回す余裕がない。」と学校現場の苦しい実情を話してくださいました。
この間大きな課題となっている教職員の多忙化解消のため、部活動の地域移行などで教職員の休日の確保する流れもあり、教職員の負担となる引率はお願いできないという配慮もあるようです。
いま公立学校の教員には時間外の賃金が支払われないとする「公立教員給与特別措置法」いわゆる「給特法」によって、学校の先生は定額働かせ放題の状態にあります。そのため時間外勤務を増やすことにつながる部活動の指導や休日出勤となる引率は先生にとって大きな負担となります。こうした状況にある先生方にできるだけ負担をかけないようにするために部活動の数を絞り、地域移行をすすめるという校長先生の配慮は十分に理解できます。
子どもたちの活躍の場が狭められないよう、時代に合わせた対応を
一方で、「部活動」での参加を前提とする大会には参加ができなくなる子どもたちは、この部活動縮小の流れでうまれる犠牲者ともいえると思います。また、いまはオリンピックにも次々と新しい競技種目が加わるなど、子どもたちが行う競技自体が多種多様となっています。部活動縮小の流れと同時に、競技種目の多様化によって部活動での活動を前提にはできない状況は珍しくないものとなっていると思います。
こうした状況にも気を配り、子どもたちの活躍の場が十分に確保されるように学校側、教育委員会、そして政治の場でも改善にむけて取り組む必要があると感じています。